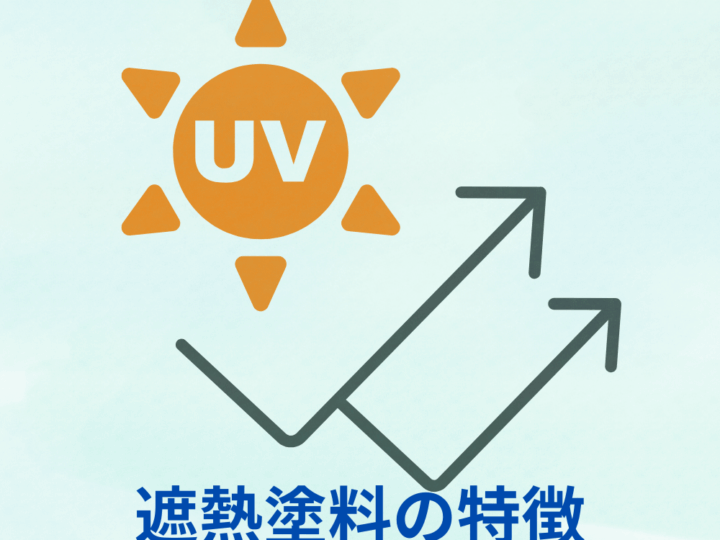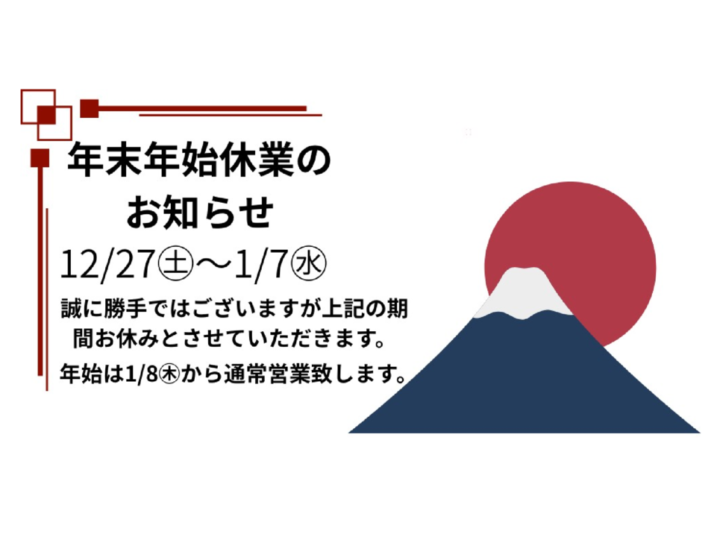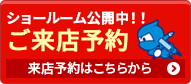2026.02.21 更新
外壁工事で起こる「ブリード現象」とは?原因と対処方法を徹底解説
ライトペイント髙井です。 もう2月も後半に差し掛かって暖かい日が増えましたね。 今回はシーリング(コーキング)工事で起こる現象を紹介致します。 外壁工事で起こる「ブリード現象」とは?原因と対処方法を徹底解説 外壁塗装やシーリング工事を行った後に、「塗装したはずなのに黒ずんできた」「目地まわりだけ変色している」といった症状が出ることがあります。 その代表的な原因のひとつがブリード現象です。 今回は、外壁工事におけるブリード現象の仕組み、発生原因、放置するリスク、そして正しい対処方法までを、ブログ用に詳しく解説します。 ブリード現象とは? ブリード(bleed)とは「にじみ出る」という意味です。 外壁工事においてのブリード現象とは、 シーリング材(コーキング材)に含まれる可塑剤(かそざい)が表面に染み出し、塗膜を変色させてしまう現象 のことを指します。 特に以下のような部分に発生しやすいです。 サイディングボードの目地部分 窓まわりのシーリング部分 外壁のひび割れ補修箇所 打ち替え・増し打ちを行った箇所 見た目の特徴 黒ずみ ベタつき ホコリが付着して黒くなる 塗膜がまだら状に変色する 特に白やベージュなどの明るい外壁では、非常に目立ちます。 なぜブリード現象が起こるのか? 原因は主に「可塑剤」にあります。 可塑剤とは? 可塑剤とは、シーリング材を柔らかく保つために配合されている成分です。 これにより、目地の動きに追従できる柔軟性が保たれます。 しかし、時間の経過や紫外線、熱の影響によって、この可塑剤が表面へ移行し、上に塗装された塗膜を汚染してしまうのです。 ブリードが発生しやすい条件 ① ノンブリードタイプではないシーリング材を使用した 従来型のシーリング材には可塑剤が多く含まれています。 現在では「ノンブリードタイプ」の材料も多く流通していますが、コストを抑えるために旧タイプを使用すると発生リスクが高まります。 代表的なシーリング材メーカーとしては、 コニシ セメダイン サンスター技研 などがありますが、各社ともノンブリードタイプを販売しています。 ② 下塗り材を使用していない シーリングの上に直接塗装すると、可塑剤が塗膜へ移行しやすくなります。 本来は「ブリードオフプライマー」などの専用下塗り材を塗布してから上塗りを行う必要があります。 ③ 塗料との相性が悪い 特に水性塗料は可塑剤の影響を受けやすい傾向があります。 材料の相性を考えずに施工すると、数か月で症状が出ることもあります。 ブリード現象を放置するとどうなる? ブリードは見た目だけの問題と思われがちですが、実は以下のリスクがあります。 1. 美観の著しい低下 外壁は住宅の印象を決める重要な要素です。 黒ずみが出ると築年数以上に古く見えてしまいます。 2. 汚れが付着しやすくなる 可塑剤がにじみ出た部分はベタつくため、ホコリや排気ガスが付着しやすくなります。 3. 再塗装が必要になる 症状が進行すると、部分補修では済まず、再塗装が必要になるケースもあります。 ブリード現象の対処方法 では、実際に発生してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか? 【軽度の場合】 ① 表面の清掃 中性洗剤やアルコールで軽く拭き取ることで、ある程度改善する場合があります。 ただし、根本的な解決にはなりません。 【中度〜重度の場合】 ② シーリングの撤去・打ち替え 最も確実な方法は、 既存シーリングを撤去 ノンブリードタイプを使用 専用プライマー塗布 再塗装 という工程を踏むことです。 ③ ブリードオフプライマーを使用 再塗装時には「可塑剤移行防止プライマー」を塗布します。 これにより、可塑剤が塗膜に移行するのを抑制できます。 予防策が最も重要 ブリードは「起こってから直す」よりも「最初から防ぐ」方が圧倒的に重要です。 ① ノンブリードシーリングを選ぶ 現在主流となっている「NB(ノンブリード)」と記載された製品を選ぶことが基本です。 ② 施工手順を守る 適切な乾燥時間を守る プライマーを必ず塗布する 相性確認を行う これらを徹底することで、発生リスクは大幅に下がります。 業者選びも重要なポイント ブリードは「材料選定」と「知識不足」が原因で起こることがほとんどです。 以下のような業者は要注意です。 材料の説明をしない ノンブリードの説明ができない 工程説明が曖昧 反対に、施工前に 使用材料の商品名 シーリングの種類 下塗り材の有無 を明確に説明してくれる業者は信頼度が高いといえます。 まとめ 外壁工事におけるブリード現象は、 シーリング材に含まれる可塑剤がにじみ出て塗膜を変色させる現象 です。 発生原因 可塑剤入りシーリング材 下塗り不足 材料の相性不良 対処法 ノンブリード材への打ち替え 専用プライマー塗布 再塗装 予防策 材料選定の徹底 正しい施工手順 信頼できる業者選び 外壁塗装は決して安い工事ではありません。 だからこそ、見た目だけでなく「数年後も美しい状態を保てる施工」が大切です。 ブリード現象を正しく理解し、長持ちする外壁づくりを心がけましょう。塗装の豆知識

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求