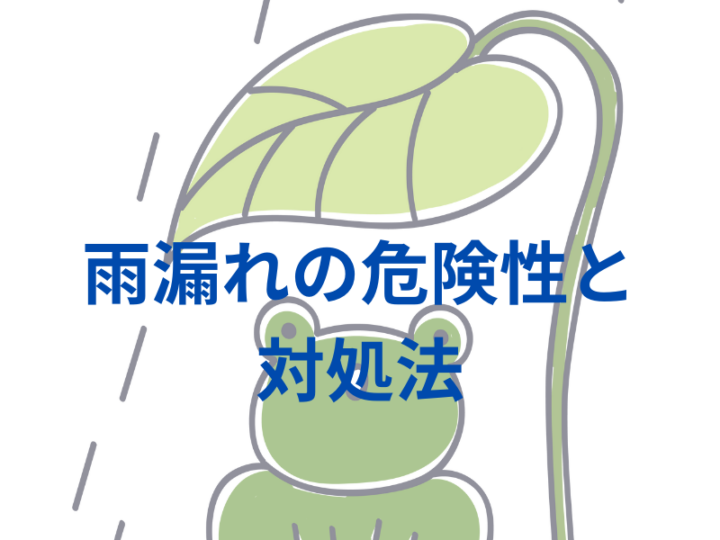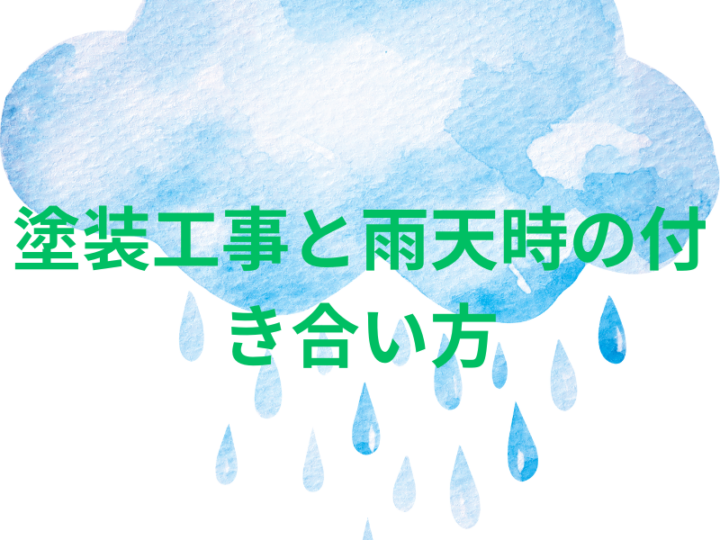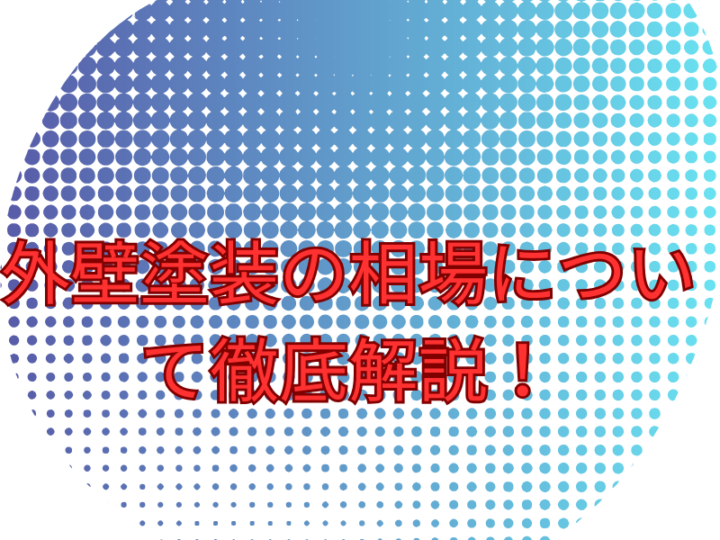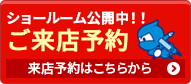2025.07.12 更新
外壁の塗り替えサイン チョーキングとは?
ライトペイント髙井です。安城市、刈谷市、知立市を中心に西三河で外壁塗装、防水工事をしております。 宜しくお願い致します! 長く安心して住める住環境を整えましょう! ■ チョーキングとは? チョーキング(白亜化現象とも言います)とは、外壁の表面を手で触れたときに、白い粉が手に付く現象です。 この白い粉の正体は、塗料に含まれている顔料(色の元)や樹脂が紫外線や雨風により分解・劣化したものです。 ■ チョーキングが起こる原因 チョーキングは、次のような要因によって発生します: 紫外線による劣化 外壁は日中ずっと太陽光にさらされています。特に紫外線は塗料の樹脂成分を破壊し、分解された顔料が粉状になります。 風雨や排気ガスの影響 雨風によって塗膜が少しずつ削られ、排気ガスや汚染物質との化学反応でも塗膜が弱っていきます。 耐用年数の超過 どんな塗料も永遠には持ちません。耐用年数(おおよそ10〜15年)を超えると塗膜が劣化し、チョーキングが起こりやすくなります。 ■ チョーキングの見分け方 誰でも簡単に確認できます。次の方法でセルフチェックしてみましょう: 外壁の色がくすんで見える。 外壁を手で触ってみる。 手に白っぽい粉がつけばチョーキングが起きている証拠。 💡注意点:チョーキングは白系の壁だけでなく、赤や青、黒系の壁でも起こります。その場合、手につく粉の色もその壁の色になります。 ■ チョーキングが起きるとどうなる? チョーキング現象が見られるということは、塗膜が機能を果たしていない状態です。以下のようなリスクがあります: 防水性の低下:雨水が壁に染み込みやすくなり、ひび割れやカビ、コケの発生につながります。 美観の悪化:粉っぽく色ムラが起き、見た目が古びて見える。 外壁材の劣化促進:塗膜が外壁材を守れなくなり、雨や紫外線の影響を直接受けるようになります。 ■ チョーキングが出たらどうすればいい? チョーキングが発生したら、外壁塗装のタイミングです。放っておくと以下のような問題が起こるため、早めの塗り替えをおすすめします。 塗膜の再形成:新しい塗料を塗ることで、外壁の保護性能や防水性能が復活します。 下地補修:塗装前に劣化した部分を補修することで、より長持ちする外壁になります。 外観リフレッシュ:色褪せた壁がきれいに生まれ変わり、見た目の印象もアップします。 ■ チョーキングが出ていない場合でも… 一部の塗料(無機塗料や高耐候性塗料など)は、チョーキングしにくい性質があります。 したがって、チョーキングが出ていない=塗り替え不要とは限りません。 他にも以下のような症状がある場合は要注意です: クラック(ひび割れ) 塗膜の剥がれや浮き カビや藻の発生 サイディングの反りや目地の割れ ■ まとめ チェックポイント 内容 チョーキングとは? 塗料の劣化で白い粉が出る現象 発生の原因 紫外線、雨風、耐用年数の経過 確認方法 外壁を触って粉が手につくか 発生後のリスク 防水性低下・美観劣化・外壁の傷み 対応策 早めの塗り替え・補修塗装の豆知識

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求