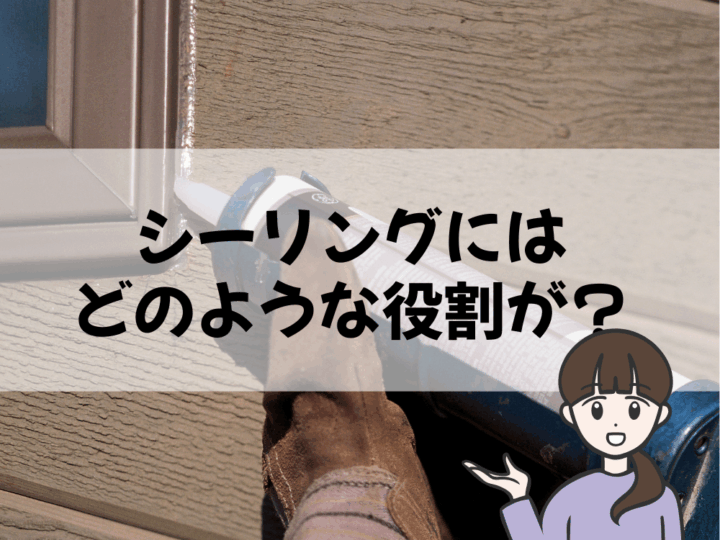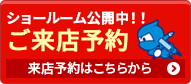2026.02.09 更新
🏗️ 塗装の寿命は「塗る前」に決まる!プロが断言する【下地処理】が最も重要な理由
💡 はじめに:化粧も塗装も「下地」が命! 皆さま、こんにちは! 外壁塗装を検討する際、「どのメーカーの塗料にするか」「何色に塗るか」に意識がいきがちではありませんか?もちろん、塗料選びも大切ですが、実はそれ以上に重要なことがあります。 それが「下地処理(したじしょり)」です。 どれだけ高級で耐久性の高い無機塗料やフッ素塗料を使っても、この下地処理が不十分であれば、わずか数年で剥がれたり、ひび割れたりしてしまいます。逆に言えば、下地処理さえ完璧であれば、塗料の性能を100%引き出し、お家を長持ちさせることができるのです。 今回は、一般の方にはあまり知られていない、でもプロが最も心血を注ぐ「下地処理」の世界について詳しくお話しします。 【この記事でわかること】 下地処理を怠ると発生する恐ろしいトラブル 塗装のプロが行う具体的な下地処理の4工程 良い業者と悪い業者を見極める「見積書のチェックポイント」 ライトペイントが下地処理に絶対に妥協しない理由 1. なぜ下地処理が必要なのか?放置した際のリスク 下地処理とは、簡単に言うと「塗料がしっかり張り付くための土台作り」です。これを怠ると、以下のようなトラブルが発生します。 🚨 リスク1:わずか1〜2年での「剥がれ」 外壁には、長年の汚れ、苔、古い塗膜のカス(チョーキングの粉)が付着しています。これらを落とさずに上から塗るのは、「泥だらけの手に絆創膏を貼る」のと同じです。すぐにベロリと剥がれてしまい、大切なお金が水の泡になってしまいます。 🚨 リスク2:ひび割れの再発(雨漏りの原因) 外壁にある小さなひび割れを無視して塗料を被せても、建物の動きによってひびはすぐに再発します。適切な補修を行わない塗装は、ただの「目隠し」に過ぎず、雨水の浸入を止めることはできません。 🚨 リスク3:表面の凹凸や仕上がりの悪さ サビや古い塗膜の段差を平らにしないまま塗ると、光の当たり方で壁がデコボコに見えてしまいます。せっかく綺麗にするための塗装なのに、見た目が残念な結果になってしまいます。 2. プロの仕事はここが違う!下地処理の4大工程 私たちライトペイントが徹底して行っている、下地処理の具体的な内容をご紹介します。 ① 高圧洗浄(またはバイオ洗浄) まずは強力な水圧で、汚れ、苔、カビ、古い塗膜を根こそぎ洗い流します。ライトペイントでは、カビの胞子まで分解する「バイオ洗浄」を推奨しており、塗料の密着力を極限まで高めます。 ② ケレン作業(サビ落とし・目荒らし) 鉄部や木部などに行う作業です。ヤスリや工具を使ってサビを落とすだけでなく、あえて表面に微細な傷をつける「目荒らし」を行い、塗料との接触面積を増やして食いつきを良くします。 ③ クラック補修(ひび割れ処理) ひび割れの種類に合わせて、シーリング材を充填したり、Vカット(ひびを広げて奥まで補修材を入れる)を行ったりします。「ただ埋めるだけ」ではなく「動いても割れない」補修を行います。 ④ 下塗り(プライマー・シーラー塗布) 下地処理の仕上げであり、塗装の第1工程です。傷んだ下地に塗料を吸い込ませて固め、上塗り塗料との「接着剤」の役割を果たします。下地の傷み具合を見極め、最適な下塗り材を選ぶのがプロの腕の見せ所です。 3. ここで見極める!信頼できる業者の見積書 下地処理は、塗装が終わってしまうと外からは見えなくなります。そのため、残念ながらこの工程を簡略化して安く見せる業者も存在します。見積書をチェックする際は、以下の点に注目してください。 ❌ 悪い例: 「下地処理一式」「塗装工事一式」 → 何をするのか不明確です。洗浄も補修も適当に済まされるリスクがあります。 ✅ 良い例: 「高圧洗浄(〇〇㎡)」「クラック補修(Vカット工法)」「ケレン作業(1種・2種など)」 → 具体的な工法や数量が明記されているかを確認しましょう。 4. ライトペイントが下地処理に「命」をかける理由 私たちライトペイントの社訓は「見えないところこそ、美しく」です。 塗装工事のクレームの9割は、実は「下地処理不足」が原因です。私たちは、大切なお家を20年、30年と守り続けるために、以下のことをお約束します。 洗浄後の乾燥時間を守る: 洗浄後、完全に乾かないうちに塗ると剥離の原因になります。私たちは天候を見極め、十分な乾燥時間を確保します。 写真による工程報告: お客様が確認できない下地処理の様子をすべて写真に収め、工事完了後に報告書としてお渡しします。 下地に合わせた最適な補修: サイディング、モルタル、ALCなど、壁材ごとに最適な補修材と工法を選択します。 結び:長持ちする塗装の正解は「土台」にあります 外壁塗装は、安ければ良いというものではありません。本当に価値のある塗装とは、「次回のメンテナンスまで、しっかりと家を守り続ける塗装」です。そのために、私たちは下地処理という「地味で大変な作業」に、どの工程よりも時間をかけます。 「うちの壁、ひび割れが目立ってきたけど大丈夫?」 「他社の見積もりに下地処理の記載がないけど…」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ライトペイントにご相談ください。プロの診断士が、あなたのお家の「土台」の状態を正確に診断いたします。塗装の豆知識

 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求